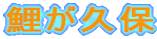|
(佐野市赤見町町屋) 赤見町の町屋から駒場へこえる山坂に、鯉が二ひき、つれ立つような形をした石があります。ここを地元の人たちは鯉が久保とよび、山仕事に来ると、必ずこのあたりでひと休みをするので、その目印の場所として、だれもが知っていました。 この町屋から駒場へこえる山は、円城院山とよばれ、昔、このあたりに夕日長者という大金持ちが住んでいたといいます。また、一方後山というところには朝日長者という夕日長者にもおとらない大金持ちが住んでいたといいます。 二人は、このへんきっての大金持ちでしたから、何かにつけては競争をし、争いをしてきました。もちろん、二人は自分の持っている宝物が一番だと、いつもいい合っては競争していました。 朝日長者には、鶴姫というそれは美しい娘がいました。夕日長者には、年ごろもちょうどいいむすこがいました。いつしか二人はおたがいに好きになり、結こんしたいと思うようになりました。 しかし、親同士は、仲が悪く、いつもはり合っているあいだがらですから、とても結こんできそうにもありません。しょう来に希望を持てない娘は、とうとう川に身を投げてしまったのです。 「ああ、どうしてなのだ。」 悲しみにくれる夕日長者のむすこも、思いなやんだ末、娘のあとを追って、同じ川のふちに身を投げてしまったのです。 二人は、そのまま鯉となって、人の世の中では、ゆるされなかった結こんを龍神の国でやっとできることになりました。 二ひきの鯉は、それはそれは仲がよく、いつもぴったりよりそって、楽しそうに泳いでいたそうです。しかし、その川も時がすぎると水がなくなり、陸になってしまったのです。それでも二人は、はなれずにぴったりよりそって、心を一つにしたまま石になってしまったといいます。今でも、この二人は円城院山から駒場へこえるひっそりとした山道のわきで、よりそっています。 ところで、あれほど争っていた朝日長者と夕日長者の二人ですが、いとしい子どもをなくしたかなしみは同じです。仲よくよりそっておよぐ二ひきの鯉を見るにつけ、意地をはり合っていた自分たちの心のまずしさに気がつき、争うことをすっかりやめました。そればかりでなく、二人は、持っていた財さんのすべてを山にうめ、お坊さんになって、これまでのつみをつぐなう決心をしました。 お坊さんになった二人は山の中に庵を建て仏様においのりを続けたそうです。その場所が今の寺久保だともいわれています。
|